INABA/SALAS FM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』1日目インタビュー書き起こし バンドの成り立ち
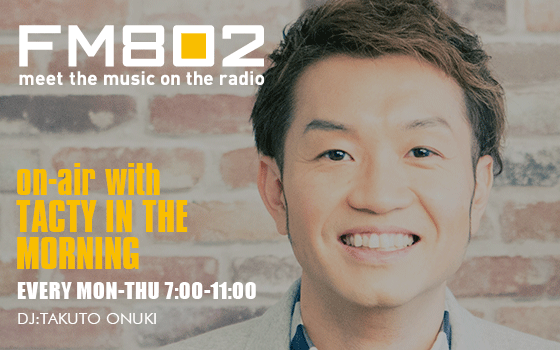
FM302の『on-air with TACTY IN THE MORNING』内でINABA/SALASのインタビューが4月13・14・15・16日の4日間にわたり放送されます。 その1日目のインタビューの書き起こしです。バンドの成り立ちなどお話しされていました。
Contents
番組詳細
| 番組名 | FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」 |
|---|---|
| 出演日時 | 4月13・14・15・16日(月-木)9:00 |
| 放送時間 | 毎週月〜金曜日 6:00~11:00 |
| パーソナリティ | 大抜卓人 |
| 番組HP | https://funky802.com/tacty/ |
2017年の「CHUBBY GROOVE」の時もインタビューから3年ぶりにインタビューに応えられました。
/
— FM802/TACTY IN THE MORNING (@TACTYfm802) April 13, 2020
今週は毎朝☀️
INABA/SALAS (@Bz_Official )
のお二人へのインタビューをOA🐓🌈
\
今日は、
✔️前回のツアーのこと🎸
✔️ユニットを組んだきっかけ👬
についてトーク🙆♂️💥
明日もおたのしみに〜✨✨
📻もう一度聴く👇https://t.co/CSI5cfdp0z#FM802 #おはたく #起きたら802 pic.twitter.com/O6cAnjUkyL
「on-air with TACTY IN THE MORNING」1日目書き起こし
大抜さん:今日はですね、fm802この南森町のスタジオを飛び出しまして、都内の某所に来ておりますけども。今日は番組でほんとスペシャルなゲストをお呼びしております。目の前にスタンバイしておりますので、自己紹介いただきます。よろしくお願いします。
稲葉さん:おはようございます。稲葉浩志です。
サラスさん:ハロー、スティービー・サラス。
大抜さん:ということで、今日はですね、稲葉さんとそしてスティービーサラスのお二人を迎えましたスティービーサラスということで来ていただいております。日本、スティービー・サラスはどれくらいぶりになるんでしょうか?
サラスさん:もうアルバムの制作に入ってたので、去年の5月からもう5.6回来日してます。
大抜さん:そうだったんですね。あの、稲葉さん。かなり今回のイナバサラスのスケジュールが相当タイトな中、動いていたんじゃないでしょうか?
稲葉さん:そうですね。タイトというのか、5月から始まったんですけど、その時に例えば、1週間東京で曲作りの作業して、それからまた一回彼が帰ったあと、しばらく空いて、またその一ヶ月後にまた1週間作業して、という細切れの作業をして。 彼はアイデアがあったんですけど、そのアイデアを形にしていくという、やっては途切れ、やっては途切れ、というすごくストレスはあったんだと思うんですけども。そういう作業上の流れは結構大変でした。
大抜さん:昨年の稲葉さんのスケジュールを見てみると、他にも色々と動きのあった年だったと思いますけれど、よく出来ましたね。
稲葉さん:そうですね。だから最初はほんとスティービーがアイデア持ってて、それをこう僕に聴かせたりしながら。そういう速度は遅かったんですけども。まあ、いろんな音選んで入れて仮歌を入れてみたいな感じで、だんだん進んでいたという感じですかね。
大抜さん:「CHUBBY GROOVE」というアルバムが出たタイミングの時に一度インタビューをさせて頂いて、その時のコンセプトはスティービーに聞いたんですけど、クールじゃないとダメなんだってのがまず最初にコンセプトにあったと思います。 その後ライブがあって私も”なんばhatch”に行ったんですけど、その時のね、あの「TROPHY」の最後の大コーラスが未だに忘れられない。オーディエンスの熱狂ぶりが凄かったですけど、あれは未だにどうしようか覚えてるんですか2017年の”なんばhatch”。
サラスさん:本当に覚えています。毎晩のように覚えていて。というのはあの曲あの部分っていうのはアメリカのネイティブアメリカンインディアンのミュージシャン達と一緒に撮ったんですね。わざわざその地域に行って。なので、その毎晩、日本で日本のファンの皆さんがその”チャント”を、ネイティブアメリカンの戦争に行くときの”チャント”をちゃんと歌ってくれたっていう様子をビデオで送り返してたんです。ちゃんと日本人の心に響いてるよっていうことで。
大抜さん:稲葉さん。あと終わり方っていうか大シンガロンっていうのはじつは各地で巻き起こってたんですね?
稲葉さん:そうですね。よくあることですが、ツアーの最初は割と決めたサイズでっていう風に終わってたんですけど。だいたいツアーが続いていくとどんどんノリが良くなってですね。だんだんなんかその一回”チャント”のみんなで歌うとこは終わって、みんながステージにラインナップして終わるってなってもスティービーがまた客を煽り始めちゃって「また始まっちゃったよ」みたいなことも(笑)
大抜さん:(笑)。そうでしたね。終わらないという(笑)。それだけオーディエンスが求めていたということで。セットリストも稲葉さんがソロでやってらしゃった曲も織り交ぜたり。
稲葉さん:そうですね。
大抜さん:あれはそこでしか観れないスペシャルなものだったという風に思いますけれども。もともと稲葉さんとスティービー・サラスはプロジェクトを通して、最初から長くじつは知り合いだったんですよね。
稲葉さん:知り合いとしてはもう、、、何年かもわからないですけれども。一緒にこのイナバサラスやる前から知り合いで。よくあったり連絡取ったり、ご飯食べに行ったりしてましたね。あとソロでもギターを弾いてもらってたんで。
大抜さん:やっぱり、昔から知ってて、ソロでも一緒に仕事する。このパートタイムであっても、一緒にバンドやってなると、「あ、こうなんだ」っていう発見と、もしかしたら「うまくいかないかもしんない」ってのはあるかもしれないですけど、やってみて「いい」って思った?
稲葉さん:思ったより大変みたいな。イナバサラスをやるにあたって、彼のファンキーでハードなギターと自分のロックスタイルのヴォーカルが組み合わさって、ハードなファンクロックみたいな感じになるんだろうな、みたいな感じで考えてたら全然違うものになって。簡単に想像できるものじゃなかったので、そこに至るまでのプロセスが試行錯誤の連続で。だから一緒にやってよかったなとすぐ思える感じじゃなくて。もっと大変でしたね。 彼もソングライターで、やっぱりギターで頼んでるときはギタリストとして来るから。僕の曲で弾いてもらったりするわけじゃないですか。 ただ一緒にやるとなると、彼が書いた曲の中で、彼の思うヴォーカルスタイルを僕が見せていけなかったりするし。そういう意味では自分も時と場合によってはスタイルを変えるじゃないけど、違うアプローチもどんどん試していかなきゃいけない。そういう意味での大変さはありましたね。
大抜さん:このスティービー・サラスはこの INABA/SALAS を立ち上げる時に”どこにもないもの”っていうのを一番最初のコンセプトに多分持っていらっしゃって。それ聞いたことないようなファンキーでロックなサウンド、それが多分最初にあったので。うまくどういう風に方向性として進めて行くのはわかんなかったっていうところにもたぶん行き着いたのかなと思うんですけど。 そこらへんのサウンドメイク、最初の目標とはそこだったんじゃないかなと思うんですが。
サラスさん:僕がというよりは、稲葉さんと二人でっていう感じだったんですけれども。最初はゲーム感覚で、こんな形になるっていうのも想像してなかったので、最初は曲ありきだったんですけれども。 例えば、”稲葉さんが歌って、スティービー・サラスが演奏する”みたいなそういうのにはしたくないよね、っていうのがあったので。 自分たちがルールを決めて、まず”シンセベースが入ってなきゃいけない”っていうことと、ドラムも”相当でかいファンキーのドラム”じゃなきゃいけないとか、”ギターもクラッシュ風”なのがいいよねとか、そういう楽しく考えてたらこういうサウンドができたっていうことだったんですけれども。 知らない間にどんどん進んでたっていう形ですね。未だに同じルールがあるんですけれども、バンドが進化していくように僕達もどんどん変わってた。
オンエア楽曲
INABA / SALAS “Demolition Girl”
INABA / SALAS "CHUBBY GROOVE TOUR 2017"セットリスト
- SAYONARA RIVER
- 苦悩の果てのそれも答えのひとつ
- ERROR MESSAGE MC
- NISHI-HIGASHI
- マイミライ
- シラセ MC
- ハズムセカイ
- 正面衝突~Do Your Own Thang~正面衝突
- Moonage Daydream
- MY HEART YOUR HEART MC
- WABISABI MC メンバー紹介
- OVERDRIVE
- MARIE
- AISHI-AISARE アンコール
- BLINK MC
- Police On My Back
- TROPHY
Submit your review | |
一緒にやってよかったなとすぐ思える感じじゃないってのは興味深いですね。
試行錯誤して作られたというINABA/SALASのサウンドの話を聞くと、「CHUBBY GROOVE」ももう一度聴き返したくなります。
